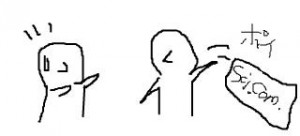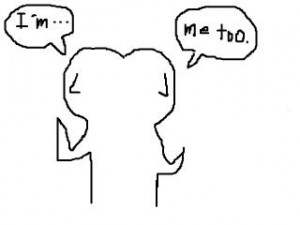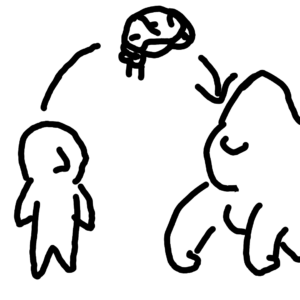いつも繰り返される「科学技術か科学・技術か」というネタと同じく「科学技術コミュニケーションって何」「そんな職業ない」というのも既にワンパターン芸の域に達しているネタです。
こちらのネタについて色々議論があることはよい事かと思いますが、昨今ちらほら見かける「科学技術コミュニケーションは役に立ってない」という結論はあまりに大雑把で短絡的に過ぎるでしょう。
しかしこの役立たず論は科学技術コミュニケーションを再考する上で重要です。
「科学」が世の中の何の役に立っているかと聞かれれば、基礎科学をやっている人は「いやぁ、直接的にすぐに社会に役立つわけではないですよ」と言うでしょう。
科学技術コミュニケーションも同様です。すべての科学技術コミュニケーションがいわゆるすぐ役に立つものとは限らない。これはいつも議論されているように、人によって「科学技術コミュニケーションの定義が違う」からです。
もちろんこういった指摘は科学技術コミュニケーションが、直接的問題解決のためのアプリケーションとして期待されていることの裏返しであり、その点が手薄であることも非常に重要な事実です。
また、確かに自己実現のための同質的集団による「科学技術コミュニケーション」は、きっかけとしては大切ですが、限定的な意義しかないのも同意できます。
にしても、「定義が違う」「役に立たない」というネタを繰り返していても、まぁそれもいいのですが、若干不毛です。
この若干不毛ないつもの件から考えることがあるとすれば、なぜ定義が違うという議論が繰り返されるのか、ということでしょうか。
この原因の一つは、狭義の科学教育と科学技術コミュニケーションが不明瞭に融合してしまい、それとは異なる概念、方法、組織がまだ未分化な点にあるのではないかと思います。
つまり、従来の活動と明確に違わない延長線上として科学技術コミュニケーションを行っているからこそ、新たな実態を伴わない、定義ありきの議論になっているということです。
実態があればわざわざ「科学技術コミュニケーション」などというジャーゴンを使う必要もないでしょう。
ここで言う「従来の活動」とは研究内容の発信です。
例えば以下の科学技術コミュニケーションの定義の主語に注目。
科学技術の専門家集団が自分たち以外の社会の様々な集団や組織と科学技術に関して意思疎通をはかる活動(小林、2007)
主語が「科学技術の専門家集団」となっています。
(言葉尻を捕らえるようで申し訳ありませんが、考えのきっかけとして・・・)
この定義は、現状の科学技術コミュニケーションに、それを担う組織、人材の偏りという構造的問題、そしてそれに起因する定義の限界があることを端的に表しているように思えます。
科学技術コミュニケーションに限ったことではありませんが、科学技術を担う組織が科学技術コミュニケーションを行う場合、どうしてもconsumer drivenではなくprovider drivenになる傾向があります。
大学や研究機関が単独で、研究や専門教育の延長で活動している限り、本質的にはprovider drivenからは抜け出せないでしょう。
(専門家の責任としての倫理、科学技術コミュニケーション活動の必要性は言うまでもありません。また、実際問題として、いい意味での世話好きから始まる「おしつけーション」が科学技術コミュニケーションの駆動力でもあるのも事実です)
コミュニケーションが「参加者が相互理解に到達するために,互いに情報を創造し分かち合う過程(ロジャーズ、1995)」「科学というものの文化や知識が、より大きいコミュニティの文化の中に吸収されていく過程(ストックルマイヤーら、2003)」とすれば、狭義の科学技術リテラシーである固定的知識を身に着けさせる、学校制度下における科学教育は、ちょっと思い切ったことを言えば、科学技術コミュニケーションではありません。
もちろん、科学教育も構成主義的学習観で見れば、学習によって各人に新しい知識が主体的に構成されるという点ではコミュニケーションです。
しかし、知識的にも制度的にも非対称性が強調される学校という場においては科学に関してethicalな話題やpoliticalな話題については議論されないし、最も重要な点として、そもそもその学びの内容や、必要性自体が否定されることもありません。
これはprovider drivenである科学者による「楽しい科学を伝える活動」にもある程度共通のではないでしょうか。
どちらも体系化された知が元にあり、それを伝えるという構造があります。
狭義の科学教育と科学技術コミュニケーションをあえて対蹠的に捉えるとしたら、科学技術コミュニケーションは非常にRadicalなものであると言えます。(本来、教育・学習とはRadicalなものであるという議論もありますが、あくまで現状の学校教育(国家制度としての義務教育)や科学技術コミュニケーションをさして、ということです)
ちゃぶ台を、返し返され科学技術コミュニケーション。
震災によって顕在化した「役立たず論」は、科学技術コミュニケーションそのものをひっくり返した、という点で示唆に富みます。
「科学って楽しい、何て言ってる場合じゃない」ということで、「今そこにある危機」に対応できる職業として正確な情報を伝える「役に立つ」コミュニケーション論が叫ばれているわけです。
これは学問分野別に体系化された知を伝えるという科学教育的科学技術コミュニケーションと異なり、問題解決型の活動で、非常に重要です。
ただ、今回の災害で急に叫ばれたような、危機においてのみ役に立つ科学技術コミュニケーションの機能をフォーカスするように思える議論は少々近視眼的で、やはりその機能が未分化であることが見え隠れします。
実例をもとに考えてみましょう。
以下のような気象学会が出した声明が話題になりました。
当学会の気象学・大気科学の関係者が不確実性を伴う情報を提供、あるいは不用意に一般に伝わりかねない手段で交換することは、徒に国の防災対策に関する情報等を混乱させることになりかねません。放射線の影響予測については、国の原子力防災対策の中で、文部科学省等が信頼できる予測システムを整備しており、その予測に基づいて適切な防災情報が提供されることになっています。防災対策の基本は、信頼できる単一の情報を提供し、その情報に基づいて行動することです。会員の皆様はこの点を念頭において適切に対応されるようにお願いしたいと思います。
緊急時において、責任ある組織が一元的に迅速に情報を発信することは必要不可欠です。
そしてそこでどのような時に、どのような情報を、どのような場で、どのような人を対象に発信するかという情報デザインとその担い手が求められます。
しかし、実際問題として国がそれをできていたかというと、そうではありませんでした。
学会がやるべきことは、独自に動いた研究者を牽制することではなく、中枢的な組織が機能できない場合にそなえて、今後、平時のうちに学会がある程度の指針と情報統合の仕組みを作っておいて、事がおきれば各研究者が独自に動きやすい仕組みをつくっておくことでしょう(あとそれができなかったことに対する反省)。
研究者の独自性とその情報源の分散性に頼るのは、コミュニケーションにおける対話に対する過度の期待と同様、問題の解決を遠ざけてしまう可能性があります。
話はもどって、危機においてはコミュニケーション的、対話的な情報創造ではなく、迅速な導管的な情報伝達もやはり重要です。
もちろんこれが非常時に成り立つには(許されるには)、そして実際に発信された情報を理解し、信頼するかどうかは、平時にどれだけコミュニケーションが積み重ねられてきたかに依存するでしょう。
そういう意味で、科学教育も、楽しさを伝える狭義の科学技術コミュニケーションも、そしてちゃぶ台をひっくり返す科学技術コミュニケーションも重要なのはいうまでもありません。
ということで、科学技術コミュニケーションを考えるうえでは、
・provider drivingではなく、consumer drivingであり、問題解決的であること
・伝達/創造される情報だけではなく、それをやりとりする仕組みを構築すること
・どのような状況において、何を目標としているのか
についてもっと自覚的である必要があるでしょう。
まだまだ私たちは科学技術コミュニケーションが何であるか分かっておらず、育てていく必要があるのです。
いつもの件で長々書いてしまいました。これにて終わり。